【男性介護職が育休を取るという選択】〜家族と仕事の両立に悩むあなたへ〜
こんにちは。介護歴20年、現役の介護主任をしているみしょです。
今回は、介護現場でまだまだ少ない「男性の育休」について、現場のリアルな声を交えてお話しします。
私が働く特別養護老人ホームでも、ここ数年ようやく男性職員が育児休暇を取るケースが増えてきました。
しかし実際のところ、「取りたいけど言い出せない」「職場に迷惑をかけるのでは」と悩む男性職員がほとんどです。
この記事では、そうした“現場の葛藤”を正直にお伝えしながら、
介護主任として感じた「男性育休の価値」について深掘りしていきます。
■ 男性介護職が育休を取りにくい現場の現実
介護職という仕事は、常に人手不足です。
誰かが休めば、残りの職員でシフトを回すしかありません。
とくに夜勤のある職場では、「一人抜けるだけで回らなくなる」と考える人も多い。
だから、育休を申し出ること自体が「悪いことをしているような気がする」と感じてしまうのです。
私の職場でも、ある若い男性職員がこんなことを言いました。
「妻が出産するんですけど、育休…取らないほうがいいですよね?」
私は即答しました。
「そんなことはない。家族を支えるのも立派な“ケア”だよ」
介護職という仕事は、人の生活を支えるプロです。
その“ケアの本質”を、一番理解しているのは私たちのはず。
であれば、自分の家族の生活を支えることだって、立派な介護の延長線上にあるのです。
■ 育休を取った男性職員が気づいた「心の変化」
育休を実際に取った男性職員に、復帰後に話を聞いたことがあります。
彼はこう言いました。
「夜中の授乳で眠れない日々が続いて、正直しんどかったです。
でも、“眠れないってこういうことか”と身をもって知りました。
今まで利用者さんの夜間不眠に“そんなに辛いのかな”って思ってたけど、今は全然違う。
あの人たちは、本当に頑張ってるんだなって思えるようになりました」
この言葉を聞いたとき、私は思いました。
育休は「休む時間」ではなく、「気づく時間」なんだと。
子どもをあやしながら、思い通りにならない現実に向き合う。
その経験が、介護現場での“寄り添い方”に深みをもたらすのです。
■ 育休を取る前にやっておくべき3つの準備
介護主任として、育休を取りたい男性職員に必ず伝えているのが、次の3つです。
① 上司に早めに相談する
シフト制の介護現場では、調整期間が命です。
できれば出産予定の2〜3か月前には相談を始めましょう。
早く言えば言うほど、職場も「支える体制」を作りやすくなります。
② 収入と給付金を事前に確認する
育休中は「育児休業給付金」が支給されますが、手取りは普段の約67%。
それでも、雇用保険に入っていれば申請すれば受け取れます。
事前に生活費を試算しておくことで、精神的にも余裕が生まれます。
③ 家事と育児の分担を夫婦で決める
「育休を取った=家事の全てを任される」わけではありません。
夫婦で得意・不得意を話し合い、できる範囲を明確にしておくことが大切です。
■ 介護職だからこそ気づける“家族ケア”の大切さ
介護職は日々、利用者やご家族の生活を支える仕事です。
その中で「支える人の支えがどれだけ大切か」を痛感している方も多いでしょう。
しかし、自分自身の家庭となると話は別。
「仕事を優先してしまう」「家族に我慢させてしまう」そんな声を何度も聞いてきました。
私も介護主任になりたての頃、同じように悩んでいました。
夜勤続きで子どもと顔を合わせる時間が減り、妻に「あなたがいないほうが楽」と言われたこともあります。
その言葉をきっかけに、私は“家族との時間も介護の一部”と考えるようになりました。
家庭を安定させることが、自分の仕事の質を高めることにもつながるのです。
■ 現場で育休を支える仕組みを作る
私が主任として意識しているのは、「育休を取りやすい雰囲気」を現場につくること。
たとえば、男性職員が育休を取ることを前提に、
・シフトの共有化
・多能工化(誰でも複数の業務ができる)
・パート職員の短期契約枠の活用
など、仕組みとして整えておくことが大切です。
「人が抜けても回る現場」を作れば、誰かが育休を取るたびに慌てなくてすみます。
それは、次に続く人たちへのバトンでもあります。
■ 育休を取った男性が職場に戻ってから感じた“変化”
育休から復帰した男性職員は、皆どこか穏やかです。
焦ることが減り、人に優しくなったように感じます。
ある職員はこう言いました。
「子どもが泣いても、“泣いてるだけでいい”って思えるようになった。
前は利用者さんに“泣いたら困る”って思ってたけど、今は“感情を出せることがすごい”って思えるんです」
この言葉は、介護の原点そのものです。
人の感情を受け止める力こそが、介護職にとって一番のスキルだと思います。
■ 育休を取ることは、“弱さ”ではなく“覚悟”
介護の世界では、まだまだ「男が休むなんて」という空気があります。
でも、私は思うのです。
「家族のために休む」ことは、逃げではなく“責任ある選択”だと。
現場を一時的に離れることで、見えてくるものがたくさんあります。
子どもや家族と向き合う時間は、自分の“生き方”を見つめ直す時間でもあります。
それを経験した人が、また現場に戻り、利用者や同僚に優しくなれる。
そんな職場の循環が生まれたら、介護業界全体がもっと温かくなるはずです。
■ 家事・育児の負担を軽減する選択肢も
育休中は、どうしても“やることの多さ”に押しつぶされがちです。
そんなときは、無理をせずプロの手を借りてください。
家事代行サービス「イチロウ」なら、掃除や料理はもちろん、育児中の家事サポートにも対応。
育児・介護の両立で疲れた家庭を支えてくれる存在です。
「少し手を借りる」ことで、家族との時間や自分の心の余裕を取り戻すことができます。
家事代行は贅沢ではなく、“支え合いの形のひとつ”です。
■ まとめ:育休は“家族を守る力”を育てる時間
男性介護職の育休は、まだまだ少数派です。
でも、一人でも多くの男性が「取ってよかった」と言えるようになれば、業界は確実に変わります。
介護の仕事は、人を支え、寄り添う仕事。
家庭もまた、小さな“ケア”の積み重ねです。
育休を取ることで学べることは、現場のマニュアルには書いていません。
それは“人を想う力”です。
家庭を大切にすることは、仕事を疎かにすることではありません。
むしろ、より深く「人を支える力」を磨く時間です。
あなたが勇気を持って育休を取ることが、職場の未来を変える一歩になるかもしれません。
介護も、家庭も。
「支える」ことの意味を、もう一度見つめ直す時間にしてみませんか。
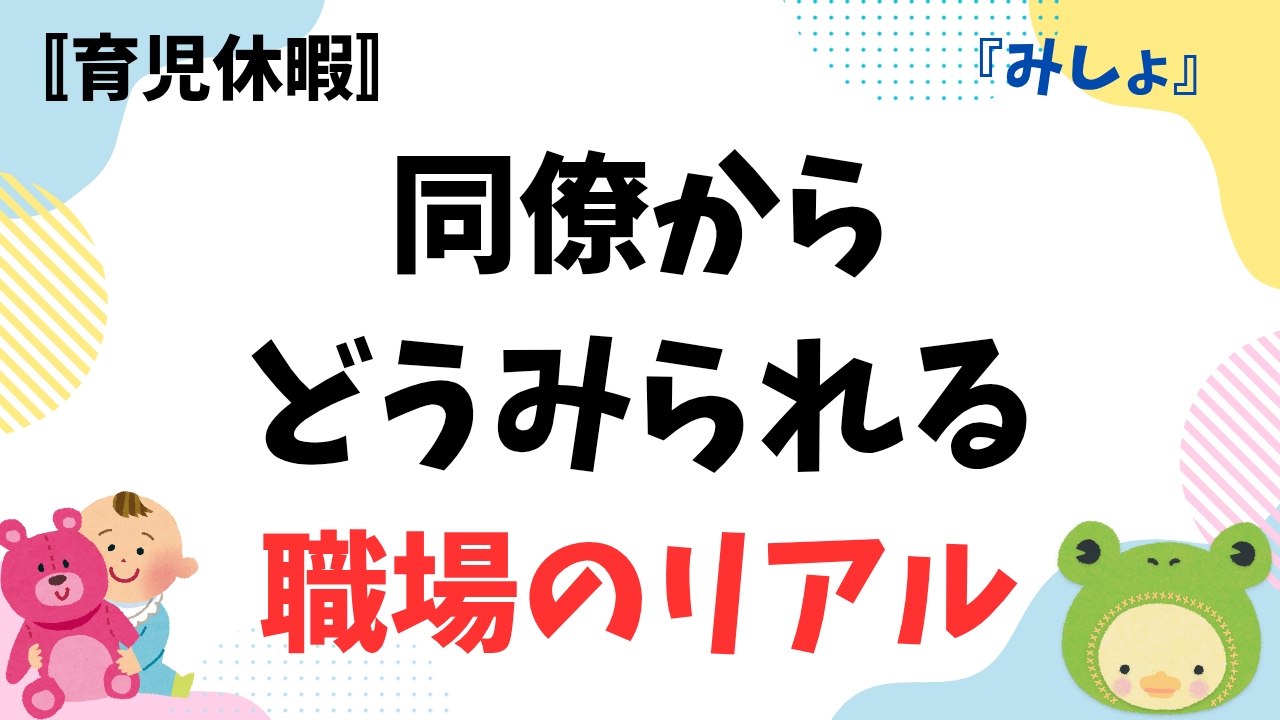
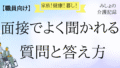
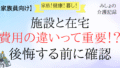
コメント