【2025年最新】育児休暇の制度・給付金まとめ|育休中はいくらもらえる?実質手取り100%の仕組みも解説!
✔️ 育児休暇 本当の現在の完成版!(2025.6.29 更新)
はじめに
2025年4月の法改正により、育児休業に関する制度は大きく変わりました。特に注目すべきは、「実質手取り100%相当」で育休が取得できる仕組みの導入と、「産後パパ育休」の拡充です。
これにより、これまで「収入が減るから育休が取りづらい」と感じていた家庭でも、安心して制度を利用できる環境が整いつつあります。本記事では、2025年最新の育休制度の全体像、給付金の仕組み、申請の注意点、そして実際にどのくらいもらえるのかを具体例を交えて徹底解説します。
制度の全体像
厚生労働省が定める育休関連の給付金は、2025年現在以下の4種類が柱となっています。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
- 育児休業給付金(一般的な育休手当)
- 出生後休業支援給付金(2025年4月新設)
- 育児時短就業給付金(2025年4月新設、時短勤務者向け)
これらを組み合わせることで、休業初期から復職後の働き方まで一貫してサポートを受けられるようになっています。
主な給付金の内容
出生時育児休業給付金
いわゆる「産後パパ育休」に対して支給される手当です。
- 産後8週間以内に、最大28日間取得可能(分割可)
- 支給率:休業開始時賃金日額×日数×67%
- 上限日額:15,690円 → 最大28日で約29万4,344円
- 有期契約社員も条件を満たせば対象
育児休業給付金
最も多くの人が利用する一般的な育休手当です。
- 対象:原則子が1歳未満(保育所入所不可などの場合、最長2歳まで延長可)
- 支給率:
- 最初の180日 → 賃金の67%
- 181日以降 → 賃金の50%
- 支給上限:67%時で月額31万5,369円、下限 ≒ 5万7,666円
出生後休業支援給付金(新設)
- 両親がそれぞれ14日以上育休を取得すると対象
- 最大28日間、賃金の13%を追加支給
- 育児休業給付金と合算すると80%支給 → 社会保険料免除と合わせて実質手取り100%相当に
育児時短就業給付金(新設)
- 子が2歳未満で、時短勤務を選択した場合に支給
- 収入減をカバーする目的で創設
- 支給額は勤務状況により異なる
【PR】育休中の家計に不安がある方へ
育休手当だけで足りるかな?将来の教育費や住宅ローンは大丈夫?
そんな方には無料の家計診断サービスがおすすめです。
✔ 無料で相談できる
✔ 将来設計もサポート
✔ 保険や資産形成もまとめて見直し
支給額の仕組みと期間
育休手当は「休業前の賃金」を基準に算出されます。ここでは代表的なモデルケースを紹介します。
年収300万円の場合
- 月収:約25万円
- 最初の6か月 → 約16.7万円(67%)
- 7か月目以降 → 約12.5万円(50%)
年収500万円の場合
- 月収:約41万円
- 最初の6か月 → 約27.4万円(67%)
- 7か月目以降 → 約20.5万円(50%)
年収700万円の場合
- 月収:約58万円
- 上限適用 → 67%時で月額31.5万円まで支給
- 高収入世帯は上限額を意識する必要あり
給付金の合算と「手取り100%相当」の仕組み
新設された出生後休業支援給付金(13%)を組み合わせると、育児休業給付金の67%と合わせて80%支給となります。
さらに育休中は社会保険料と所得税が免除されるため、実際の手取りは勤務時と同等、もしくはそれ以上になるケースも多いのです。
この仕組みは特に「収入が減るから育休を諦めていた」家庭にとって、大きな後押しとなります。
延長・追加申請の注意点
育休を延長する場合、特に保育園入所不可の証明が必要です。
- 市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」が必須
- 2025年からは申請期限が厳格化、遅れると不支給の可能性あり
- 会社経由での申請が基本だが、フリーランスや自営業は直接申請
申請書類は自治体や勤務先で配布されますが、不備があると手当が遅れるので注意が必要です。
企業・事業主の義務
企業にも育休支援に関する義務が課されています。
- 個別周知・意向確認(従業員に対する説明責任)
- 育休に関する研修実施
- 相談窓口の設置
- 従業員1,000人以上の企業は育休取得率の公表義務
これにより、従業員が「育休を言い出しにくい」雰囲気を減らすことが期待されています。
よくある失敗例
- 申請を会社任せにしていたら、期限を過ぎて支給が遅れた
- 配偶者と同時期に育休を取らず、両親14日ルールを満たせなかった
- 高収入なのに上限額を把握しておらず、想定より支給が少なかった
こうした失敗を防ぐためには、制度の詳細を早めに確認しておくことが大切です。
働き方別のポイント
正社員
会社が申請を代行してくれる場合が多いが、申請状況のチェックは必須。
パート・有期契約社員
雇用保険の加入条件(週20時間以上・31日以上の雇用見込みなど)を満たしていれば対象。
フリーランス・自営業
育児休業給付金の対象外。代わりに国民年金保険料免除や各自治体の独自支援を活用する必要あり。
配偶者との「シェア型育休」
両親がそれぞれ育休を取得すると追加給付が受けられるため、夫婦でシェアして取得する家庭が増えています。
特に父親が14日以上取得することで、出生後休業支援給付金の対象となり、実質手取りが増えるメリットがあります。
【PR】育休後のキャリアに不安がある方へ
「育休から復帰したけど、このまま今の職場でいいのかな?」
そんな方におすすめなのが介護・医療・福祉業界に強い転職サービスです。
✔ 無料で登録・相談OK
✔ 子育てと両立できる職場を紹介
✔ 非公開求人多数あり
まとめと今後の展望
2025年の改正により、育休制度はこれまで以上に利用しやすくなりました。特に「実質手取り100%」で取得できる仕組みは、家庭の経済的不安を和らげ、大きな安心材料となっています。
さらに時短勤務者への給付金や、企業の義務化によるサポート体制の強化も進み、今後は「育休を取るのが当たり前」の時代にシフトしていくでしょう。
これから育休を検討する方は、早めに会社や配偶者と相談し、最適なタイミングで制度を活用することをおすすめします。
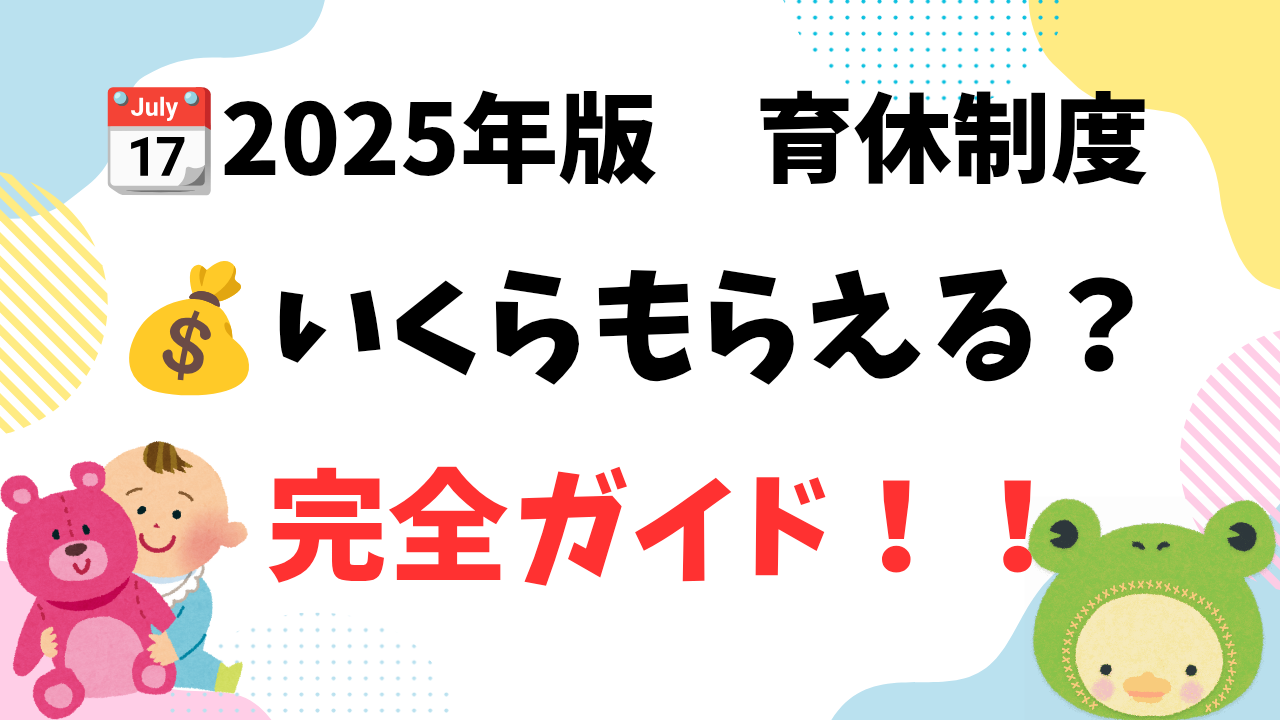


コメント