要介護・要支援の認定を受けるとどうなる?
介護保険が使えるようになるメリットを解説
はじめに
「うちの親もそろそろ介護が必要かも…」
「でも、要介護とか要支援の認定って、本当に必要?」
そんなふうに迷っている方へ。
実はこの“認定”を受けることによって、利用できる制度や支援が一気に広がります。
認定を受けるかどうかで、介護生活の「負担」も「安心感」も大きく変わるんです。
この記事では、現役の介護主任である筆者が、「要介護・要支援の認定を受けると何が変わるのか?」を現場目線で分かりやすく解説します。
1. 要介護・要支援認定を受けると「介護保険サービス」が使えるようになる
認定を受ける最大のメリットは、介護保険サービスを利用できるようになることです。
この制度を知らないままだと、すべての介護サービスを「全額自己負担」で受けなければなりません。
しかし認定を受けると、利用料の自己負担は1〜3割に軽減され、プロの支援を経済的に受けられるようになります。
主な介護サービスの例
- 訪問介護(ヘルパーによる掃除・買い物・調理支援)
- デイサービス(送迎付きで入浴・機能訓練・食事提供)
- ショートステイ(数日間の宿泊型介護サービス)
- 福祉用具レンタル(車いす・歩行器・ベッドなど)
- 住宅改修(手すり設置・段差解消などの補助)
これらはすべて、認定があることで「介護保険の支給対象」となります。
たとえば、デイサービスを自費で使うと1回あたり8,000円以上になることもありますが、保険を使えば2,000円前後まで抑えられるケースも。
介護費用の差は、年間で見ると数十万円単位にもなることがあります。
2. ケアマネジャーがついて、介護の方向性が明確になる
要介護・要支援の認定を受けると、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がつきます。
このケアマネさんが「介護の設計図」であるケアプランを無料で作成し、利用者に合ったサービスを提案してくれます。
ケアマネジャーが行う主なサポート
- 本人・家族への聞き取り(生活状況・困りごとなど)
- 利用できる介護サービスの提案・手配
- 介護施設・事業所との調整
- 行政手続きや更新のサポート
介護が必要になると、まず「何から始めればいいか分からない」という壁にぶつかります。
ケアマネジャーは、その道案内役として、介護を“仕組み化”してくれる存在です。
特に家族介護をしている人にとって、心強い味方になります。
3. 経済的な負担が軽減される
介護サービスは、自費だと驚くほど高額になることがあります。
しかし、要介護・要支援の認定を受けることで、介護保険による自己負担1〜3割が適用され、経済的負担を大幅に軽くできます。
さらに使える“助成制度”の例
- 紙おむつ代の助成
- 介護タクシー利用補助
- 在宅介護手当(自治体による)
- 住宅改修・福祉用具購入の補助金
これらは自治体によって異なりますが、「認定がある人だけが対象」というケースがほとんどです。
つまり、認定を受けておくことで、介護費用の負担を抑えながら安心してサービスを利用できるようになります。
4. 家族の精神的・身体的負担が減る
「介護は家族の責任」――そう思い込んで頑張りすぎてしまう人が本当に多いです。
しかし、認定を受けて介護保険を活用すれば、家族の負担を分散しながら介護を継続できるようになります。
訪問介護を利用すれば、掃除・洗濯・買い物などをプロに任せることができ、
デイサービスを使えば、昼間の介護から一時的に解放されます。
「家族が休む時間を確保すること」も、介護を長く続けるためにはとても大切な視点です。
5. 早期の支援が“重度化防止”につながる
「まだ大丈夫」と思っていても、加齢とともに少しずつ身体機能や記憶力は変化します。
要支援や軽度の要介護認定を受けた段階で、リハビリや生活支援を導入することが、将来の寝たきりや認知症の進行を防ぐことにつながります。
早めにケアマネジャーとつながっておくことで、いざ状態が変化したときにもスムーズに次の支援につなげられるのです。
6. 「認定を受ける=施設に入らなければならない」ではない
多くの方が誤解していますが、要介護認定を受けても必ず施設に入る必要はありません。
むしろ、自宅での生活を支えるために介護保険は設計されています。
訪問介護・訪問看護・デイサービスを組み合わせることで、住み慣れた自宅での生活を長く維持できるケースも増えています。
認定を受けることは、「自宅での介護を続けるための第一歩」でもあるのです。
まとめ|迷うなら一度、申請してみよう
要介護・要支援の認定を受けることで、介護保険サービスの利用、費用負担の軽減、専門家の支援など、多くのメリットが得られます。
「申請したら何か変わってしまうのでは…」と不安になる方もいますが、実際には「助けてもらえる選択肢が増える」だけ。
迷っているなら、まずはお住まいの地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談してみましょう。
「まだ早い」と思う時期こそ、支援を受けるチャンスです。
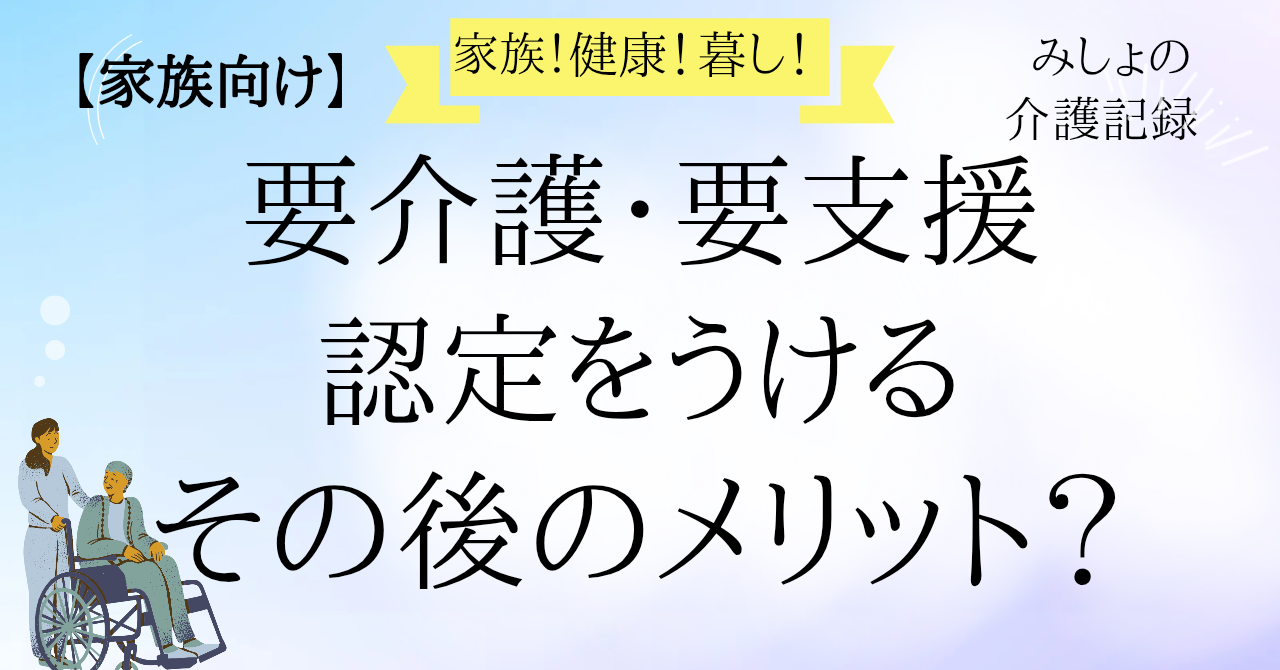

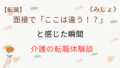
コメント