『要介護認定』ってどうやって決まるの?
〜家族が知っておきたい申請と調査のポイント〜
1. はじめに
「親がだんだん弱ってきた気がする…」「介護保険って使うには何が必要なの?」
そう感じ始めた時に、まず出てくるのが『要介護認定』という言葉です。
しかし、いざ申請しようとすると「どんな書類が必要?」「調査って何をされるの?」「不利になることはない?」と、不安や疑問が次々と出てきます。
現役の介護主任として19年、私は多くのご家族が「制度の最初の一歩」でつまずく瞬間を見てきました。
この記事では、要介護認定の仕組みや申請から結果までの流れ、調査での注意点、そして家族としてできるサポートを現場目線でわかりやすく解説します。
2. 「要介護認定」って何?
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するための資格を得る審査です。
市区町村が申請者の心身の状態を調べ、「どのくらい日常生活で介助が必要か」を判断します。
判定は以下の7段階に分かれます:
- 非該当(介護サービスは原則使えない、自立判定)
- 要支援1〜2(軽度で生活の一部に支援が必要)
- 要介護1〜5(数字が大きいほど介護度が重い)
この区分によって、使えるサービスの種類・上限金額・回数が決まります。
例えば「要支援」ならリハビリや訪問サービスが中心ですが、「要介護」になると入浴介助や施設利用なども可能になります。
3. 認定までの流れをざっくり解説
要介護認定の流れをわかりやすく整理すると、以下の通りです:
- 市役所で申請(本人・家族・ケアマネジャーが代行も可能)
- 認定調査(市職員や委託業者が自宅・施設で面談)
- 主治医意見書(病院に依頼し、健康状態や既往歴を記載)
- 審査会(一次判定:コンピュータ、二次判定:専門家による確認)
- 結果通知(申請から約30日で郵送)
ここで注意すべきは「認定結果が出ないと原則サービスが使えない」こと。
ただし急ぎの場合は、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、結果が出る前にサービスを使うことも可能です。
4. 自宅に来る「認定調査」って何をされるの?
認定調査は、本人の生活状況を確認する大切な場面です。
調査員がチェックするのは主に以下の5分野:
- 身体機能:立つ・歩く・座る・階段の昇降など
- 生活動作:食事・排泄・入浴・着替え
- 認知機能:記憶力・理解力・時間や場所の把握
- 精神・行動面:感情の安定、徘徊や妄想の有無
- 社会生活:服薬管理・買い物・金銭管理
調査時間は30分〜1時間程度。
会話の受け答えや、動作を見ながら「できる/できない」を客観的に記録します。
例えば、普段は家族が支えてやっと立ち上がれる方が、この日だけ気合で立ってしまう…というケースもよくあります。
その場合、調査結果は「自立」と判断され、実際より軽く判定されてしまうこともあります。
5. 実は“非公開”な審査会の裏側
認定調査と主治医意見書をもとに、コンピュータが一次判定を出します。
その後、医師や看護師、ケアマネなどで構成される介護認定審査会が最終判定を行います。
審査会のメンバーは本人と会うことはなく、書類とデータだけで判断します。
つまり、調査当日の様子や主治医の意見書が判定を左右するのです。
現場でよくあるのは、
「調査員に“今日は元気そうですね”と言われてしまい、実際より軽く判定された」
「主治医が普段の生活状況を十分に把握していなかった」など。
6. 調査で損しないための注意点
調査の場面で損をしないために、家族が意識しておきたいのは以下の点です:
- 本人に“普段通り”で臨んでもらう(無理して元気に振る舞わない)
- 困りごとを事前にメモ(転倒回数・トイレの失敗・夜間の徘徊など)
- 必要な時だけ補足説明
例:「昨日も転倒があったのですが本人は覚えていません」
ただし、過度に口を挟むと「家族が介護できている」と誤解されることもあるので、冷静に事実を伝えることが大切です。
7. 家族ができるサポートとは?
申請から結果が出るまでの間、家族がやっておくと良いサポートは以下です:
- 主治医に生活状況を伝える
→ 意見書に反映されやすくなる - ケアマネや包括支援センターに相談
→ 制度やサービス選びのアドバイスが得られる - 記録を残す
→ 転倒・排泄・服薬などを簡単にメモしておく
特に調査日当日は家族が立ち会うことが重要です。
本人が「大丈夫」と言ってしまう場面でも、家族が補足すれば実態が伝わります。
📢 広告①:施設探しのサポート
要介護認定の結果によっては、「自宅介護」か「施設入所」かという大きな選択が迫られます。
そんなときに頼れるのがこちら👇
マイナビあなたの介護
![]()
安心できる老人ホームを探すならマイナビ介護|専門スタッフが無料でサポート
8. まとめ:正しく知って、焦らず申請を
要介護認定は「介護保険サービスの入り口」であり、これを正しく受けることで、介護生活の選択肢が大きく広がります。
- 元気そうに見えても、生活に支障があれば申請してOK
- 「普段通りの姿」を見てもらうことが正確な判定につながる
- 不安なら地域包括支援センターに相談してみる
介護は「最初の一歩」が最も不安で大変です。
ですが、その一歩を踏み出せば、次の支援や制度利用につながり、家族の負担も確実に軽くなります。
📢 広告②:介護の知識を学びたい家族へ
「もっと制度や介護のことを理解したい」
「自分のために介護資格を取ってみたい」
【未来ケアカレッジ】
![]()
未来ケアカレッジ|介護資格の取得で“知識と安心”を手に入れる

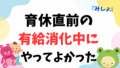

コメント