はじめに
「親が介護を必要としているかも…」「でも、何をすればいいの?」
そんな不安を抱えているあなたへ。
介護は、ある日突然やってくるものです。
そして、多くの人が“初めての介護”に戸惑いながらスタートします。
実際に介護が始まると、
「どこに相談すればいいの?」「お金はどのくらいかかるの?」「自分にできるのかな…」と、分からないことだらけ。
そんな時こそ焦らず、一歩ずつ進めることが大切です。
この記事では、介護を始める人が「最初にやるべきこと」を、現役介護主任の立場から分かりやすく5つのステップで解説します。
ステップ1:まずは現状を冷静に把握する
介護のスタート地点は、「今、どんなサポートが必要か」を見極めることです。
「食事は自分でできているか」「歩行に不安がないか」「夜間のトイレは大丈夫か」など、日常生活の動作を具体的に観察しましょう。
たとえば次のような視点で整理します:
- 食事・入浴・排泄などの日常動作に支障があるか?
- 物忘れが増えていないか?
- 気分の変化(怒りっぽい・無気力など)がないか?
- 転倒やふらつきが増えていないか?
- 夜間に徘徊や不安を訴えることはないか?
こうしたチェックをしていくうちに、「自分でできること」と「手助けが必要なこと」が見えてきます。
この情報が、後の要介護認定やケアプランづくりにとても役立ちます。
もし医療面で気になることがある場合は、早めにかかりつけ医に相談し、健康状態を把握しておくのがおすすめです。
ステップ2:市役所で「要介護認定」を申請する
介護サービスを利用するためには、介護保険制度に基づく「要介護認定」が必要です。
申請は本人や家族が、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで行います。
申請後は「訪問調査員」が自宅を訪問し、生活の様子やできる動作を確認します。
その後、主治医の意見書をもとに審査が行われ、介護度(要支援1〜2・要介護1〜5)が決定します。
結果が届くまでの期間はおおむね30日ほど。
緊急の場合は「暫定利用」もできるので、市役所で相談してみてください。
ここで多くの人が不安に思うのが「申請手続きが難しそう…」という点。
ですが、地域包括支援センターでは申請書の作成や提出を代行してくれる場合もあります。
「ひとりで抱え込まない」ことが何より大切です。
ステップ3:利用できる介護サービスを知る
認定結果が出ると、介護保険を使える範囲が決まります。
たとえば、要支援1・2なら「デイサービス」「訪問介護」などの軽度支援。
要介護3〜5になると「特別養護老人ホーム」「ショートステイ」などの施設利用も可能になります。
サービスの一例は以下の通りです。
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問看護
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具レンタル・住宅改修
- 施設入居(特養・老健・サ高住など)
どのサービスを利用するかは、介護度だけでなく「本人の希望」や「家族の負担」も考慮して決めます。
「何を優先したいのか」を家族で話し合うことが、後悔しない介護の第一歩です。
ステップ4:ケアマネジャーを味方につける
介護サービスを使う際、中心的な存在となるのが「ケアマネジャー(介護支援専門員)」です。
ケアマネは、要介護者と家族の状況を把握しながら、最適な介護プラン(ケアプラン)を立ててくれます。
ケアマネの主な役割は以下の通りです。
- 必要な介護サービスの調整・手配
- 利用者や家族の希望を反映したケアプランの作成
- 事業所との連携や情報共有
- 状態変化に合わせたプランの見直し
「ケアマネは相談しやすさが命」と言われるほど、信頼関係が大切です。
相性が合わなければ変更も可能なので、遠慮せず伝えましょう。
良いケアマネに出会えると、介護の不安が一気に軽くなります。
そして、介護サービスを支える現場には、介護職員や看護師、理学療法士など多くの専門職が関わっています。
あなたがもし「介護の仕事をしてみたい」「家族の介護経験を活かしたい」と思うなら、資格取得を目指してみるのも良い選択です。
ステップ5:親の気持ちを忘れずに
介護を始めると、どうしても「やってあげなきゃ」という気持ちが強くなります。
でも、本当に大切なのは“親の気持ち”を尊重することです。
- 「自分のことはできるだけ自分でやりたい」
- 「家族に迷惑をかけたくない」
- 「自分の生活リズムを保ちたい」
介護とは、「助けること」だけではなく、「相手の尊厳を守ること」。
できる限り本人の意思を尊重し、対話しながらサポートする姿勢が大切です。
時にはうまくいかず、感情がぶつかることもあるでしょう。
そんな時は「自分も人間だから疲れて当然」と思ってください。
介護者の心のケアも同じくらい大切なのです。
まとめ
介護は、誰にとっても“初めての経験”です。
最初から完璧を目指す必要はありません。
今日できる小さな一歩を積み重ねることが、やがて大きな安心へとつながります。
この記事で紹介した5つのステップをおさらいしましょう:
- ステップ1:現状を把握する
- ステップ2:要介護認定を申請する
- ステップ3:介護サービスを知る
- ステップ4:ケアマネと連携する
- ステップ5:本人の気持ちを尊重する
介護は「制度」と「人の思い」が重なって成り立つものです。
制度を知ることで不安は減り、人の思いを大切にすることで、介護は優しい時間に変わります。
あなたの一歩が、きっと家族の笑顔につながりますように。
そしてもし、介護を仕事として関わってみたいと思ったなら、
「かいご畑」で自分に合った働き方を探してみてください。
介護の世界には、あなたの優しさを必要としている人が必ずいます。

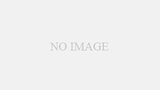

コメント