育休前、シフト調整で苦労したことベスト3|介護主任のリアル体験記
こんにちは、介護主任のみしょです。
今日は「育休前のシフト調整で苦労したことベスト3」について、私自身の経験を交えてお話しします。
介護の仕事はシフト制で回していく現場なので、誰かが休みに入るとその分を埋める必要があります。育休は当然の権利ですが、現場では「おめでとう!でも…シフトどうする?」という現実的な問題がのしかかってくるんですよね。
この記事では、実際に私や同僚が育休に入る際に起きたリアルなシフト調整の苦労を振り返り、共感できる部分や「あるある!」と感じられる場面をお伝えします。
第3位:急に穴が開く…夜勤シフトの調整地獄
まず第3位は「夜勤シフトの調整」です。
介護施設では夜勤要員が限られていて、数人しか回せない場合も多いんですよね。私の施設でも夜勤可能な職員は片手で数えるほどしかいませんでした。そんな中で、ある職員が育休に入ることになったとき、夜勤シフトの組み方が一気に崩れました。
たとえば、ある月の勤務表を作成しているときのこと。夜勤は月に4〜5回必要ですが、夜勤ができる人が1人減るだけで他の職員の夜勤回数が一気に増えます。「え、私6回も夜勤入るの?」と驚く同僚。「ごめん、でもどうしても回らないんだ…」と謝るしかない私。内心では「これ、誰か体壊すんじゃ…」とヒヤヒヤしていました。
特に育休前の職員は「最後だからこそ夜勤に入れない」ケースもあります。妊娠中で体調に配慮が必要だったり、医師の指導で夜勤禁止になっていたりするためです。その分の穴を埋めるのは、結局ほかの職員。休み希望を調整し直したり、夜勤回数を平等に分けるために頭を抱えたり…。夜勤表とにらめっこしながら「誰かもう一人だけでも夜勤できる人がいてくれたら…」と何度つぶやいたことか。
現場の空気もピリピリします。「なんで私ばっかり夜勤増えるの?」と不満が出てくるのも当然です。私自身も現場に入りながら調整する立場なので、フォローするにも限界がある。そういう意味で、夜勤シフトの穴埋めは本当に大変でした。
第2位:希望休との板挟み…「誰を優先するの?」問題
続いて第2位は「希望休と育休前調整の板挟み」です。
介護職員にもプライベートがあり、家族との時間や病院通いなどで希望休を出します。しかし、育休に入る職員がいると、その分人員が減るため「希望休が通りにくい」状況が一気に増えます。
あるとき、子どもの学校行事に参加したいと希望休を出した職員と、妊娠後期で体力的に負担を減らしたい職員の希望が重なりました。勤務表を見ながら「どちらを優先すべきか…」と悩み、頭を抱える私。結局、妊娠中の職員を優先せざるを得ませんでしたが、もう一方の職員からは「なんでいつも自分だけ我慢しないといけないの?」と不満が…。それを受け止めつつ「でも安全第一だから…」と説明するものの、どうしても角は立ってしまいます。
特に難しいのは、希望休を出した職員の事情がどちらも大切な場合です。親の介護や子どもの行事、受験、冠婚葬祭…。すべて大切で、どれも軽視できないんです。勤務表を作るたびに「誰かを優先すると、誰かを犠牲にすることになる」という重さに押しつぶされそうでした。
しかも、調整は一度で終わらないんです。勤務表を配布してからも「あの日やっぱり休めませんか?」「子どもの体調が悪くて…」と変更依頼が続きます。穴が開けばまた埋める。その繰り返し。夜な夜な勤務表を修正し、翌朝「また変わったの?」と職員に言われる…。正直、心がすり減りました。
第1位:制度と現場のギャップ…「権利」と「人手不足」の板挟み
そして第1位は「制度と現場のギャップ」です。
育休は法律で守られた大切な権利。取ること自体は当然ですし、職員も「おめでとう!しっかり休んでね」と送り出したい気持ちはあります。しかし現場は人手不足。頭では理解していても「正直キツい…」と感じる瞬間が何度もありました。
例えば、ある職員が急に切迫早産のリスクで予定より早く育休に入ったとき。準備していたシフトが一気に崩れ、残りのメンバーで回すしかなくなりました。その時点で勤務表はほぼ完成していたのに、ゼロから組み直し。しかも、その職員は本来なら夜勤も月4回入る予定だったので、まるごと誰かが背負う形に…。残業も増え、休みも削られ、現場の空気はどんどん重くなっていきました。
職員たちは「育休は権利だから仕方ない」と頭ではわかっている。でも「自分たちばかり負担が増える」という気持ちも消せない。感情と理屈の板挟みで、雰囲気がギスギスする。そんな中で私は管理職として「みんなで支え合おう」と声をかけ続けましたが、内心では「限界は近いかもしれない」と不安でした。
さらに、制度上は「育休中の職員を代替で雇えばいい」と簡単に書かれています。でも、実際には求人を出しても人が集まらない。短期間だけ来てくれる人も少ない。結局、現場メンバーでなんとか乗り切るしかないんです。このギャップこそが一番の苦労でした。
まとめ:育休は権利。でも現場を回す工夫が必要
育休は大切な制度であり、取るのは当然の権利です。しかし、介護の現場では「制度」と「人手不足」という2つの壁にぶつかります。夜勤のシフト調整、希望休との板挟み、制度と現実のギャップ…。どれも現場を悩ませる大きな課題です。
私が学んだのは、育休に入る職員と事前にしっかり話し合うこと。そして「どこまでシフトに入れるのか」「体調の配慮はどうするか」を明確にし、なるべく早く周りに共有すること。そうすることで、残る職員の心構えも変わり、調整の余地が生まれます。
また、普段から「助け合い」の文化を作っておくことも大切です。「お互い様だから仕方ないよね」と思える関係性があるだけで、負担を受け入れる気持ちも和らぎます。もちろん、それでも大変なことに変わりはありませんが、少なくとも「孤独に抱え込む」状況は避けられます。
転職を考えるあなたへ
もし「今の職場では限界…」「もっと働きやすい環境がいい」と感じているなら、転職を考えるのも一つの手です。介護業界は人材不足だからこそ、職場によって働きやすさの差がとても大きいんです。
例えば かいご畑 のような介護職専門の転職サイトでは、無資格・未経験からでも始められる求人や、育休や有給取得率が高い職場の情報をチェックできます。登録して相談するだけでも「こんな職場もあるんだ」と気持ちが軽くなるはずです。
あとがき
育休は決して「迷惑」ではなく「守られるべき権利」です。でも、その影響を受けて現場が苦労するのも事実。私は何度もその板挟みで悩みましたし、今も答えが出ているわけではありません。ただ、現場で働く仲間同士の思いやりや理解があれば、少しずつ乗り越えられると感じています。
この記事が、同じように悩む介護職の方や、これから育休を迎える方の参考になれば嬉しいです。そして「自分の働き方を見直したい」と思ったときは、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
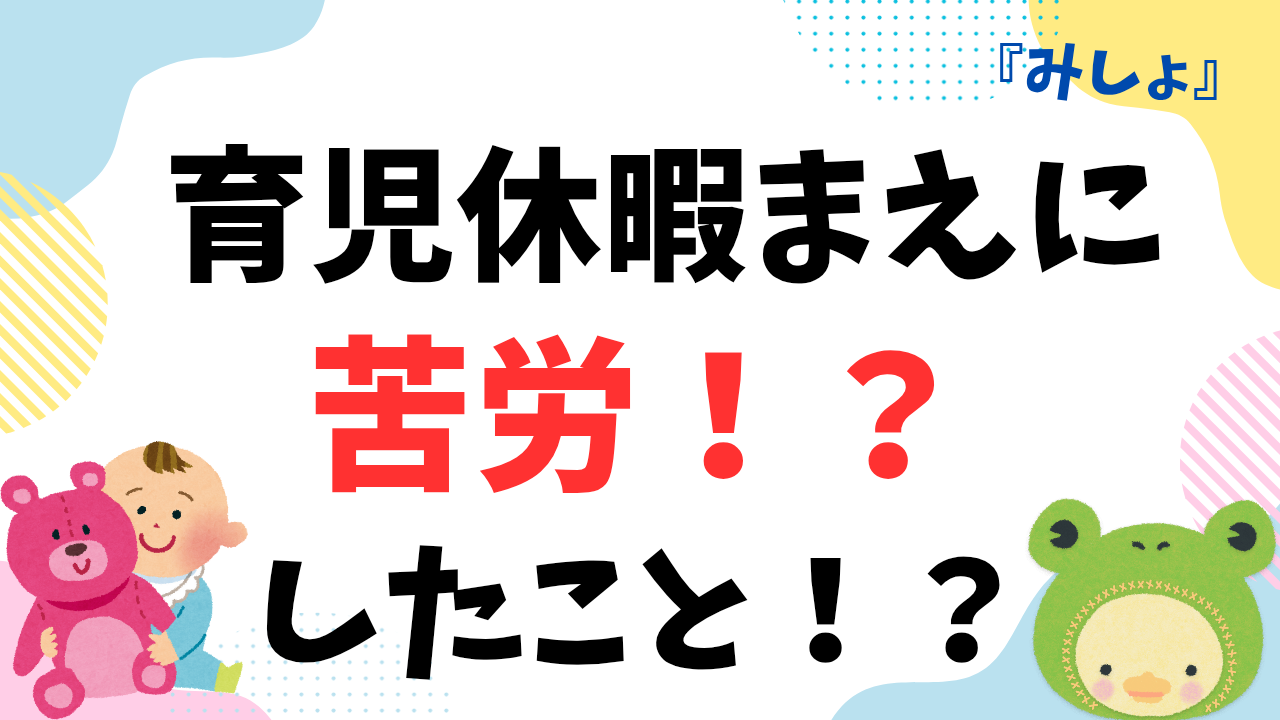
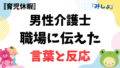

コメント