介護現場で育休を取るには?スムーズな取得のための準備と制度の基本
はじめに
介護職で働きながら、育児と両立したいと考える方も増えてきました。
とはいえ、「忙しい現場で育休って本当に取れるの?」「休む前に何をすればいいの?」と不安に感じる人も多いはず。
この記事では、介護の現場で育休を取得するために必要な準備と、制度の基本をわかりやすく解説します。
現場の体験談や具体的なステップも紹介するので、安心して次の一歩を踏み出せるはずです。
▶ 介護中の家事、プロに任せてみませんか?
スマホで簡単予約、1時間から利用可能な家事代行サービス。
![]() → 家事代行サービスCaSyを見る
→ 家事代行サービスCaSyを見る
1. そもそも介護職でも育休は取れるの?
はい、もちろん可能です。
育児・介護休業法によって、正社員・パート問わず一定の条件を満たせば育休を取得できます。
ただし「人手不足」「急な対応が多い」など介護現場ならではの特性から、職場側と丁寧に調整しておくことが大切です。
実際に現場では「人が少ないから無理では?」と感じてしまうケースもありますが、法律で守られた権利なので安心してください。
制度を正しく理解し、遠慮せずに申請することが第一歩です。
2. 育休取得に向けた基本ステップ
- 職場の就業規則・制度の確認
まずは、自分の職場にどんな育休制度があるか、何ヶ月前に申請が必要かなどを確認しましょう。
施設によっては「配偶者が専業主婦でも取得可能」「子どもが1歳半まで延長可能」など条件が異なります。 - 上司への相談は早めに
妊娠・出産の予定が分かり次第、なるべく早めに上司に伝えることがカギです。
シフト調整や後任探しにも関わるため、早期共有は信頼関係にもつながります。
たとえば「出産予定日がこの時期なので、この月から休みに入りたい」と具体的に伝えると安心感が生まれます。 - 書類準備と申請手続き
会社所定の育休申請書類や、健康保険・雇用保険に関する提出物を用意します。
給与の有無、育休給付金の手続きなども含めて、事前に確認しておくことが大切です。
3. 現場での“引き継ぎ準備”がカギ
育休取得前に最も重要なのが「業務の引き継ぎ」。
介護現場はチームで動くため、あなたが休む間に他の職員にどのように仕事をお願いするかがポイントになります。
細かい情報を残すことで、職場に安心感を与えると同時に、利用者さんの生活リズムも守られます。
- 担当している利用者さんのケア内容をメモにまとめる
- 特記事項(家族対応、服薬管理など)を記録しておく
- 他職種(看護・ケアマネ)との連携ポイントを明確にする
- 突発的な対応が必要なケースを想定してメモを残す
「ここまで準備してくれたなら安心」と思ってもらえれば、気持ちよく育休に入ることができます。
4. 職場とのコミュニケーションは“丁寧さ”がカギ
介護の現場は忙しいぶん、感情的なすれ違いが起こりやすいもの。
「育休を取る=迷惑をかける」と思いがちですが、制度は権利です。
とはいえ、相手への配慮や現場状況を理解した上で、丁寧に伝えることでトラブルなく進められます。
実際に「業務分担の提案をセットで伝えたら、スムーズに了承された」という声もあります。
ポイントは:
・「お互い様」の関係を意識する
・業務分担についての提案も合わせて伝える
・復帰後の働き方(時短勤務など)の希望も相談しておく
・メールや書面で残しておくことで、後のトラブルを避けられる
5. よくある不安とその対策
- 「現場に嫌がられない?」
引き継ぎや事前の調整をしっかり行うことで、周囲も納得しやすくなります。
また、復帰後は「ありがとう」の一言を大切にすることで信頼が戻りやすいです。 - 「復帰後に居場所がないかも…」
育休中も月1回程度、職場に顔を出す「コミュニケーション継続」がおすすめ。
メールやLINEで現場の情報を少し共有してもらうと、復帰後のギャップを減らせます。 - 「お金は大丈夫?」
育児休業給付金(原則、賃金の67%→50%)を受け取るには、雇用保険の加入が条件。
ハローワークや会社の総務に早めに確認しましょう。
また、児童手当や自治体独自の支援金も併用できる場合があります。
▶ 離れて暮らす親が心配な方へ
センサー付き見守りサービスで、スマホで様子が確認できます。
![]() → 見守りシステムを導入する
→ 見守りシステムを導入する
おわりに
介護の仕事をしながら育児をするのは本当に大変です。
しかし、制度を知り、職場と丁寧に調整することで、育休は決して不可能ではありません。
実際に「しっかり準備したことで安心して休めた」という声も多くあります。
大切なのは、無理せず助けを借りながら続けていくこと。
これから育休を考えている方の一歩が、少しでもスムーズに進むことを願っています。
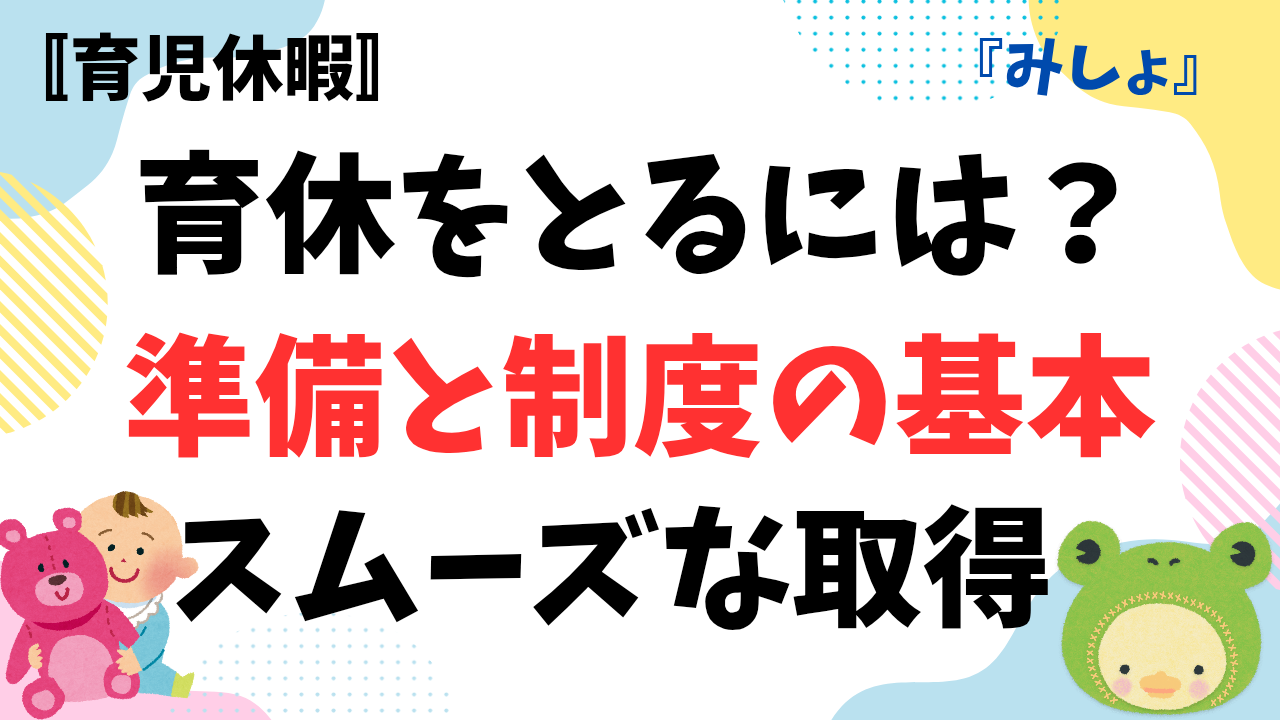
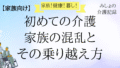
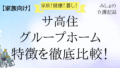
コメント